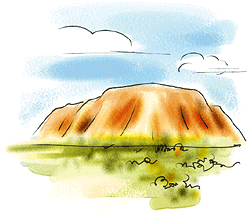今から約8年前にディケンズ・フェロウシップで親しくなった、W先生から、イギリス文学に興味があるのなら、みすず書房から出ている、ジョン・サザーランド著『ヒースクリフは殺人犯か?』『ジェイン・エアは幸せになれるか?』を読んでみては?と言われた。この本は、イギリス文学の各作品についてサザーランドの見解が書かれたもので、特に表題が楽しく、読書意欲をそそるものだった。さっそく、手に入れて読んでみたが、私がかなり読み込んだディケンズの作品についてはある程度理解できたが、それ以外の作品についてはまったく理解できず、やはりイギリス文学はじっくり読まないと評論やエッセイなども理解できないんだなと思ったものだった。その後、この2つの本で紹介されている作品を読んだし、今でも機会があれば読んでみたいと思っているので、こういういい方は正しくないのかもしれないが、手引書として役立っている。W先生には、イギリス文学についてたくさんのことを教えてもらったので、本当に感謝したい。この2つの本にはそれぞれ30余りのエッセイ(評論)が掲載されているが、この中で最も目を引くのは、「ヒースクリフは殺人犯か?」である。
『嵐が丘』を読んだ人はきっと経験したと思うが、ヒースクリフの執拗で、陰湿な攻撃、虐待は目に余るほどである。幼少の頃に辛い目に遭ったのはわかるが、3年間の失踪後、帰って来たヒースクリフは別人のようになり、あらゆる人(語り部役の家政婦(お手伝い)のネリィ・ディーンにも害が及ぶ)に攻撃、虐待を繰り返す。ヒースクリフの虐待は、復讐の対象となった、ヒンドリー、エドガァ、キャサリンだけでなく、召使のジョウゼフまで及んでいるようで、ジョウゼフはヒースクリフの悪事を黙認している。
ヒースクリフの復讐は、ヒンドリー(キャサリンの兄)の財産を奪い取ることから始まる。次にイザベラ(エドガーの妹)を誘惑し駆け落ちして結婚するが、結婚後、ヒースクリフはイザベラに虐待を繰り返し、イザベラは家を出て子供を出産して、再びヒースクリフの元に戻ることなく死亡する(黒枠付きの手紙がそれを知らせる)。またキャサリンはエドガァと結婚していたが、ヒースクリフは昔親しかったことを話してキャサリンを苦しめ、板挟みになったキャサリンを追い詰めて、死に至らせる。死の直前にキャサリンは子キャサリンを出産する。
その後もヒースクリフの復讐は続き、ヒンドリーの息子ヘアトンや子キャサリンへの虐待、エドガァの財産の没収にも及んだ。ヒースクリフの憎悪はさらに続き今度は、ヘアトン、キャサリンを死へと追いやることに注ぎ込まれるように思われた。しかし子キャサリンに防衛本能が働いたのか、それまで嫌っていたヘアトン(それまでキャサリンとヘアトンの仲は付いたり離れたりだったが)と仲良くするようになり、ヒースクリフの脅しにもヘアトンが屈しなくなったため、ヒースクリフの勢いは急激に萎びて来る。ヒースクリフはお手伝いのネリィに言っている。
「『哀れな結末だよ、まったく、そう思わんかね?』いましがた目撃した光景のことを、しばらく考えふけってから、こんなふうに語りはじめました。『俺の暴虐な行動がこんなにいきなりおしまいになっちまったということがさ!おれは二軒の家をぶちこわすために、てこだのつるはしだのを手に入れて、ハーキュリーズほどの仕事ができるように自分を訓練して、さていよいよなにもかも準備ができ、おれのしたい放題にできるようになった時に、気がついてみたら、両方の家の瓦一枚はがそうという気が、おれになくなっちまってるんだ!...(以下略)』」
復讐が完了するという直前で、子キャサリンの思わぬ反撃に遭い、ヒースクリフはやる気をなくしてしまった感じである。しかしもしこの物語が、ヒースクリフの復讐(犯罪と言いたいところだが)の完了で終わったなら、物凄く後味の悪い小説となっただろうが、そうならなかったために『嵐が丘』は不朽の名作となったと思う。ヒースクリフのような悪人が自分がしたいことをやり終えるまでを描いたなら、ポーやドイルが書いたような犯罪小説になったと思われるが、『嵐が丘』は上記の理由から、永遠の純文学となった。ただ、ヒースクリフの悪魔のような性格はこの小説を一度読んだら心に深く刻み付けられるだろう。お手伝いのネリィはロックウッドに言っている。
「そう言っているとき、灯火がヒースクリフの顔の上にひらめきました。まあ、ロックウッドさま、一目みたその瞬間に私が震え上がったその恐ろしさ、とても口では申せません!あのくぼんだ黒い両の目!あの微笑とあのすごい青い顔色!ヒースクリフさんではなくて、悪鬼としか私には見えませんでしたわ、しかもあまりの恐ろしさに蝋燭の明かりを壁のほうへ傾けたものですから、私は暗闇の中にのこされてしまいましたんです」
この小説は、人口が密集しておらず、人々が交流せずむしろ敬遠し合っているという共同体に法律に詳しい悪人が住み着いた時の恐ろしさを描き、警告を与えているようにも思える。ヒースクリフという苛烈な人物を描いたということやヨークシャーの荒野の厳しさを描いたから評価されたということもあるのだろうが、村落の人々同士の関係が希薄な場合に起こりうる危険性(ヒースクリフのような人物が付け込む恐れがあること)を描いたということにより、後の人が関心を持ったということが重要なところではないかと思う。