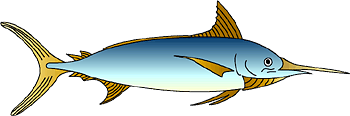
『老人と海』の翻訳を読んだのが先だったか、スペンサー・トレイシー主演のアメリカ映画『老人と海』を見たのが先だったか、覚えていない。高校の授業が終わって、高校近くの佐野書店で、手頃の厚さで装丁がすばらしい文庫本を手に取り買って帰って読み始めたのが先だった気もするし、せっかく捕獲したカジキを鮫に食い荒らされて、サンチャゴ役のトレイシーがこん棒で鮫を殴りつける印象的な場面を見たのが先だったような気もする。
アメリカ文学はそんなふうにアメリカ映画となることが多く、ヘミングウェイは『老人と海』の他、『誰がために鐘は鳴る』『武器よさらば』『キリマンジェロの雪』『日はまた昇る』も映画となっている。『誰がために鐘は鳴る』『武器よさらば』は戦争文学というカテゴリーであるし、『キリマンジェロの雪』は短編の恋愛小説なので、今後も読む機会はないと思うが、『日はまた昇る』はタイトルも意味深だしいつか読んでみたい気がする。ただ、この『老人と海』は最後のところで励まされた気になったので、今回の読後、これからもよろしくと言いたいところである。
物語は、主人公のサンチャゴが不漁続きでそれが84日間続き、少年を雇えない状態になっているという説明から入る。それでも少年は、ベテラン漁師の老人サンチャゴが大好きで、漁についての話をサンチャゴの家でしている。二人は気軽にメジャーリーグの話題を話したりもする。やがて就寝の時間になり、朝になるとサンチャゴは今日も一人で漁に出る。サンチャゴは、不漁が続いているので今日は少し遠くまで行ってみるかと思い行くことにするが、それがうまく行って、今までに捕獲したこともないような大きなカジキマグロを釣り上げた。あたりが来て釣り上げれば終わりというのではなく、相手の様子を伺いながら仕留めて釣り上げるチャンスを待つのだから、持久力と熟練の技が必要となる。大きなカジキマグロを釣り上げてすぐは、1500ポンド以上で売れるだろうとか考えてサンチャゴは幸せな気分になっていたが、銛で突いて仕留めたためすぐに血の臭いを嗅ぎつけてアオザメがやって来る。
老人はアオザメを銛の脳天への一撃で仕留めるが、銛を失ってしまう。それに続いて、鮫(ガラノ)が続々とカジキマグロ目掛けて襲ってくるが、オールの柄にナイフを縛り付けたものやこん棒で立ち向かう。自身がカジキマグロを釣り上げる際に負傷した手の傷や何日もほとんど眠らずに獲物と格闘したため、アオザメやガラノに獲物が襲われた時には獲物を守ることができない。サンチャゴは思わずカジキマグロに「おい、半分」「もとは丸一匹で、いまは半分だ。おれが沖へ出たばっかりに、どちらもひどい目に遭ったな」と声を掛けたりする。そうして獲物の半分をなくしたことを嘆き、武器(漁具)を失ってしまったことを確認するが、それでも何とか立ち直り、「戦う、おれは死ぬまで戦う」と言って、まだ自分の手のひらが自由に動くことを確認する。やがてハバナの夜景が遠くに見えて、老人に希望が出てくるが、帰港を間近にしてまたしてもガラノに襲われ、半分残っていたカジキマグロの魚肉もほとんどすべてが食いつくされてしまう。しばらくして上陸したサンチャゴは、深夜だったので少年の手助けもなく、何度もへたり込みながらマストを担いで家に辿り着く。翌朝は少年がやって来て、捜索が大変だったが、また老人と一緒に漁に出たいと言う。少年は、今度はしっかり準備すればいい。手の傷を治して漁に出ようと言う。外では観光客がサンチャゴが釣り上げたカジキマグロが大きくて立派だっただろうと褒め讃える。
以前、私は2度、新潮文庫で『老人と海』を読んだが、その時は映画の印象が強かったからか、老境に差し掛かった不漁続きの老人が、思い切って遠洋に出て漁をして大きなカジキマグロを釣り上げたが、鮫に食べ尽くされて、泣く泣く漁港に戻る。老人は漁師を引退することを考えるといった内容だったと思っていた。ところが、この翻訳でのサンチャゴは若々しく、様々な苦難にもめげずに立ち向かっていく。銛を失ったら、オールの柄にナイフを縛り付けたもの、それがなくなったらこん棒で、と戦う意志を失うことはない。帰宅してからも少年に漁のことで話を弾ましている。まるで老いても希望を失うな、支援者がきっといるから地道に頑張れと言っているように思える。
ヘミングウェイは、『日はまた昇る』『武器よさらば』『誰がために鐘が鳴る』で確たる地位を文壇に築いたが、『河を渡って木立の中へ』が不評だった。それで起死回生のために出版されたのが、この『老人と海』で最初、雑誌『ライフ』に全文掲載され、人気を取り戻すことが出来、1954年のノーベル賞受賞に繋がった。英文学ファンの私にはアメリカ文学は少し取っつきにくいが、『老人と海』は物語がよき時代のアメリカ(舞台はキューバのハバナだが)を感じさせるので好きな作品である。