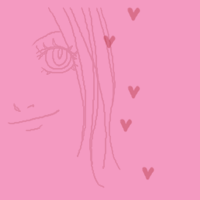
若葉の頃 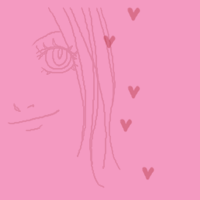
「これで最後だと思うと、少し寂しいな」
秋子はそう言って、入学して1ヶ月になる高校の門をくぐった。
秋子は、休日の通用口である校舎正面の入口を入り玄関の受付にいる警備員のおじさんに会釈すると、そのまままっすぐ歩いた。しばらく行くと左手に階段があり、それを上った。明治の頃に建造された校舎のため、重厚な木造の階段で壁面は白壁だった。3階まで上ってから右手の廊下を校門の方に歩いて行くと突き当たりに生物科教室があった。生物科教室と書かれたアクリル板の上にはその十倍程ある、「歓迎 写真部」と書かれ、カメラのイラストが描かれた横看板が針金でぶら下げられていた。一般の生徒は1学期に1、2度この教室を利用するだけだった。しかし秋子は4月に入学してすぐに写真部に入部したため、何度もこの教室に足を運んでいた。それでも休日にこの教室に入るのは、秋子も始めてだった。写真部の先輩に、日曜日にも誰かが来ているから、部活をしたいんだったらおいでと言われていた。教室の入口に鍵が掛かっているのではないかと思ったが、引き戸が動いたので、そのまま静かに開いた。
校舎は南向きに建てられていたため、秋子が左手の窓を見ると初夏の日差しが差し込んでいたが、その少し手前を見ると男性が机に顔を伏せていた。秋子が近づいてよく見てみると6人掛けの生物室の机の一つに男性が椅子に腰掛け、うつ伏せになって眠っていた。そのそばには写真現像用のバットが置かれ、中には半分程水が入っていた。男性は写真部の先輩だったので、ぐうぐうと声を出して気持ちよさそうに眠っていたが、思い切って起こしてみることにした。
「先輩、おはようございます」
先輩は喜多という名の2年生で、1週間前の連休の際の撮影会に一緒に京都に行っていた。撮影会は、京都駅から市電で銀閣寺道に出て、哲学の道、法然院のあたりを写して回った。
「ああ」と喜多は少し何が起こったのかわからない様子で口元を拭っていたが、しばらくして秋子を認めると
「君は下山さん。どうしてここに」
「それは...。それより先輩こそ、何をしているんですか」
「現像液がなくなったので、新しいのを作ろうと思ったんだけどそれにはお湯が必要なんだ。ハイポ(チオ硫酸ナトリウム)というこのグラニュー糖の粒の大きなやつみたいなのを溶かすためにね。いつもそこの準備室の窓際に置かれているコンロを使ってお湯を湧かすんだけど、生憎、どこを捜してもマッチが見つからなくて。それでこうして直射日光に当てて30度位まで水温が上がるのを待っているんだよ」
「まあ」
そう言いながらも、秋子は持っていた大きな手提げ袋を探って、ライターを取り出した。
「なぜ君が...。でも、これで待つこともなくなったわけだ」
そう言って、喜多は秋子からライターを受け取ると準備室の入口のドアを開け、窓際にあるコンロに近づいた。コンロの脇にはベージュ色の石をくり抜いた流しがあり、そこでやかんに水を入れて点火したコンロにのせた。
「これでよし。それじゃあ、現像液を作るのを手伝ってくれるかい」
「はい」
準備室を入って左上にある棚は1メートル60センチほどの高さから壁面につけられているため、棚の中を見るためには、椅子に乗らなければならなかった。
「この椅子に乗って、一番下の段に置かれている箱の中から、暗室の入口の鍵を取って。終わったら元通りにしておいて」
喜多は秋子から鍵を受け取り、ドアを開けて、暗室にしばらくいたが、分銅ばかり、木製のさじ、計量カップ、ガラスのまぜ棒、薬品が入った壜、薬品保存用壜などを順番に持ち出した。
秋子は分銅ばかりで薬品の重さを計ってそれを順番にビーカーで溶かして行くのは楽しい作業だったが、喜多に、定着液を作るので氷酢酸を混ぜてくれと言われ、プラスチック製の壜の蓋を開けた時には、顔を顰めた。
「そうだった。それ強烈に臭うの言っといたらよかったね。服にも付かないように気を付けてね」
しばらくして、暗室で使う薬品の準備ができた。
「今日、休みなのに学校に来たのは、この前の撮影会で撮影した写真を仕上げるためなんだけど、君が何か持って来ているんだったら焼いてあげるよ」
「わたし、自分でやってみたいんです」
「それなら、まず暗室の中に入ろう。今まで何度か暗室には入ったことがあるだろうから、やり方はだいたい分かっていると思う。この小さな空間は、両方に暗幕が張ってあるだろ。これは外部の光線が、暗室の中に直接入らないようにするためだ。さあ、そちらのドアを開けて暗室に入ったら、電気をつけて。正面にあるのは、引伸機というフィルムの画像を印画紙に焼きつける機械だ。半切サイズの大きさまでのモノクロ写真が作れる。引伸機の左上にランプがあるけど、あれは赤外線ランプで、印画紙に感光しない光のもとで作業を行うためのものだ。その手前がカウンターになっているけど、ここにさっき作った現像液、定着液、それから今から作る停止液をバットに入れておいて、引伸機で画像を焼きつけた印画紙を順番にここに浸すんだ。停止液は、先程の氷酢酸を3パーセントの割合で水道水に混ぜたもので、現像の作業の度に作るんだ。停止液は、現像の進行を止める。現像液はアルカリ性だが、停止液、定着液は酸性だ。定着液は、名前の通り、画像を印画紙に定着させるものなんだよ。定着液から出して約1時間流水で濯ぎ洗いし、表にある乾燥機で乾燥すれば出来上がりというわけだ」
そう言いながら、喜多は手際よく暗室作業の準備をして行った。
「ぼくたちのクラブは、2つの種類の作品を文化祭に出品するために、撮影会を月に1回行っている。半切の大きさのモノクロ写真を木製パネルに張り付けた作品を見てもらうパネル展示と三脚を使用してリバーサルフィルムで横に3枚連続した画像を撮影しBGMを流しながら見てもらうスライド映写がある。下山さんはまずは今使っているカメラでいろんなものを撮影し、自分でフィルム現像、引伸ばしをやってみるといい。でも、ここは平日や土曜日は利用者が多いから...」
「いままで何度かここに入ったことがあるんですけど、いつも人が一杯で。現像液に印画紙を浸して少し待っていると焼きつけた画像が浮き上がって来るのを見るのが面白くて、毎日授業が終わったら来ていたんですが」
喜多が、秋子からフィルムを受け取ると喜多は言った。
「きょうのところは、引伸機の取扱いはぼくからの説明だけにしてほしい。印画紙をイーゼルマスクで固定して引伸機の光を照射するのだけれど、その前にフォーカススコープを使って引伸機のピントを合わせるんだ。こうしてフィルムをセットしてと。どのコマを焼くのかな。三人の人物が写っているけど、まん中の女の子はきみのようだね」
喜多は、フィルムを返して、焼付けをした印画紙を秋子に渡した。
「さあ、これを現像液に浸してごらん。感光した薬が塗られている面を下にしてむらができないようにこの竹ばさみで手早く押さえるんだ。しばらくしたら、表を向けて。画像が現れるから、1分半から2分浸して、停止液へと移すんだ。ほら、画像が出て来た。両端にいるのはご両親なの」
「そう、始めてクラリネットを人前で演奏した時に両親と撮った写真なの」
水洗の終わった印画紙の水を一旦切って、水道水を半分程入れたバットに移し、ふたりは生物室に戻って来た。喜多が乾燥機で写真を乾かしていると秋子が言った。
「先輩、いろいろありがとうございました」
「別に礼には及ばないよ。後輩に親切にするのは当たり前のことなんだから。それより次の日曜日も君がここに来るんだったら、ぼくも来るけど」
「先輩、今日のお礼をしたいんです。準備がありますので、少しの間、目を閉じて待っていてほしいんですが...」
喜多は変なことを言い出す子だなと思った。目を閉じてみると、喜多にはわけのわからない大きな期待が膨らんで来るのがわかった。
しばらくすると神々しい楽器の音が聞こえた。喜多がはっとして目を開くと、そこには笑顔でクラリネットを演奏する秋子がいた。喜多は少し驚いたが、クラリネットの音色がとても美しかったので、曲が終わるまで静かに耳を傾けた。日だまりでのんびり憩うような曲だった。
「ブラームスのクラリネット・ソナタ第2番第1楽章のメロディーだけど素敵でしょ。わたしには、やっぱりこちらが向いているみたい。入学式前のオリエンテーションで写真部を知って、わたしも写真を一度やってみたいと考えたの。でも、部員が40人近くいて写真を好きな時に焼けないから、もう一度部室を訪れて先輩の誰かに挨拶して、明日からは音楽に励もうと思ったの。最後に親切に指導していただいて、ありがとうございました。先輩のことは、一生忘れません」
喜多は、生物室の入口のところで秋子と別れると、さっき見ていた夢の続きを期待するかのように机に伏せて寝入ろうとしたが、思い直して校門が見える窓のところに行き、秋子が通りかかるのを待った。しばらくして秋子はやって来た。秋子は校門をくぐる前に振り向き、喜多が見ているのに気が付いた。喜多が手を上げると、秋子は笑顔で何度も手を振った。